
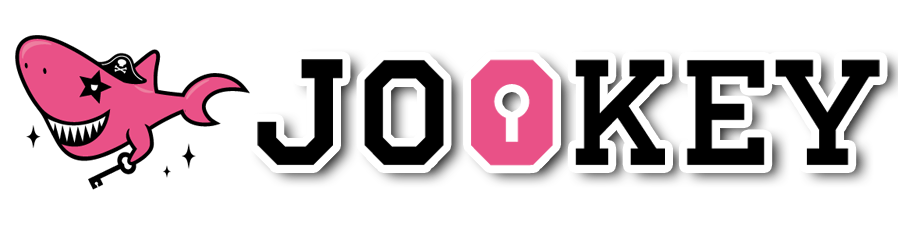

【第七話】求人誌に載らない…
「死体洗い」のバイト
「新療法の実験台で月30万円」
「買物と風呂掃除だけで日給2万円」
「添い寝で時給8,000円」……
一見簡単で高収入が付き物の「闇バイト」。
しかし、うまい話には裏があるもので『口座売買』や『出会い系サイトのサクラ』は「知らなかった」では済まされない違法行為。
では、口コミの高報酬バイトの全てが犯罪に紐付いているのかと言うと、必ずしもそうとは言い切れません。

求人誌には決して載ることのない、経験不問・高額支給のアルバイト「死体洗い」。あなたはこんな話を聞いたことがありませんか?
* * *
そのアルバイトは、公にされていない。
大学の部活などで伝統的に引き継がれていて、希望者は作業内容をみだりに口外しないよう、誓約書にサインを求められる。
管理人からゴム引きの作業着や手袋、長靴、マスクが支給され、地下室に連れて行かれる。
地下にあるタイル張りの部屋には縦横3メートルほどのプールがあり、褐色になったホルマリンで満たされている。

──そこには何体もの死体が浮かんでいる。
大学の解剖授業では、何ヶ月にもわたって献体を使用するため、痛まないよう毎回ホルマリンを吹き付ける。しかしそれだけでは不十分なため、月に1回は薬液に浸さなくてはならない。
本来なら献体を使用する医学生がやるべき作業だが、友人に肩代わりを頼んだりするうちに、口伝えのアルバイトへと変化していったらしい。
作業は、薬液に浸された献体が浮かび上がってきたら、竹竿を使って沈めるというもの。
しかし、献体が空気に触れるほど浮上することはそうそうなく、皮下脂肪が多く死後間もない女性の遺体がたまに浮き上がる程度。
1回2時間ほどの作業で、報酬は5万円。
* * *
──いかがでしょうか。
「デッキブラシの柄で突いて沈める」
「死体はベトナムで戦死した米兵」
「有名寺院の一角にある」
といった説もありますが、おおむね「地下」「薬液プール」「死体」というモチーフで一致します。
理科室で見た「ホルマリン漬け」をイメージすると、死体をホルマリンで満たしたプールに入れて保存することに違和感を感じません。
しかしこのホルマリン。正確にはホルムアルデヒド水溶液と言うのですが、実は揮発性が高いうえに毒性が高く、人体に有害なため「医薬用外劇物」に指定されています。
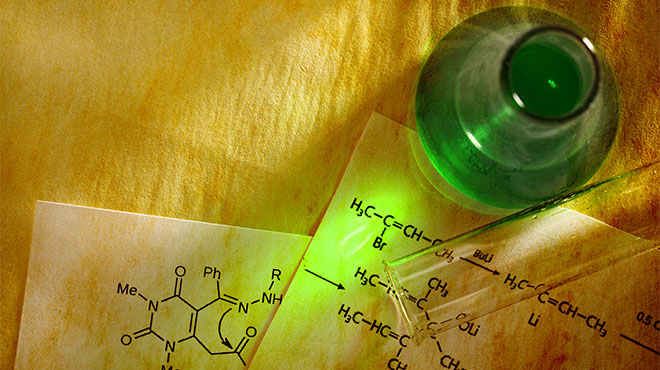
「そんなもののプールなど作れるワケがないので、これはよくできた作り話」と言うのが通説になっています。
また、1994年にノーベル文学賞を受賞した大江健三郎氏のデビュー作となった短編小説「死者の奢り」(1957年)の中に、大学病院で解剖用の死体を扱うアルバイトが登場します。
アルコール溶液のプールに浸かった死体を、新しいアルコールで満たしたプールに移し替えるというもので、そのモチーフが似ていることから「この小説が都市伝説のネタもと」という説もあります。
──ところが、
「禁じられた死体の世界―東京大学・解剖学教室でぼくが出会ったもの」(著:布施英利)には、かつて死体保存用に作られたプールが存在した旨の記述があります。
さらにそこには、こんな記載もあります。
「このプールは二年ほど前に掃除をして、アルコールを抜いた。これも業者に掃除をしてもらおうと見積もりをお願いしたが、こちらは見積もりさえも出なかった。高額だったのではない。いまどき死体の入った汚い浴槽を掃除するような職員はいない、ということだ。」引用:布施英利(1995年)「禁じられた死体の世界―東京大学・解剖学教室でぼくが出会ったもの」青春出版社
「常識ではあり得ない」と言うことだけでは「実在しない」という根拠にはなりません。
「死体洗いのアルバイト」は、かつて存在した可能性がある──
良識や道徳観からタブー視され、明るみに出る事のないグレーゾーンの中に、都市伝説は眠りつづけているのかも知れません。
<次回予告>
「タラちゃんの足音が電子音」「『んがっ、くっく』って何だ」「あなごさん、27歳」──次回は謎多き「サザエさん」にまつわる都市伝説に迫ります。それでは来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽんっ! うふふ……。